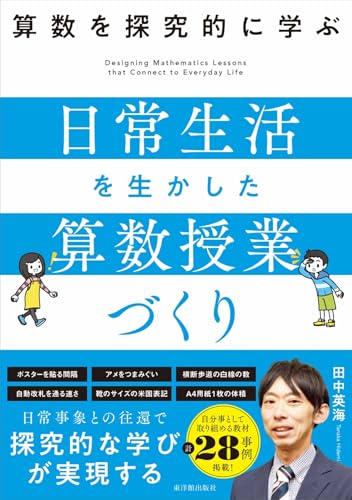「構造」の類義語の一つは「仕組み」であり,「しくみ」と書けば易しく伝えられやすい点には,異存ありません。授業の検討や実施報告などにあたり教師が見出した「構造」について,授業でしか利用できないその場限りのものである可能性にも,読む側は考慮したいところです。
今月,同時に購入した算数に関する3冊の書籍・雑誌に,「構造」の語が出現していました。
該当書のAmazonへのリンク,書誌情報,該当箇所の抜粋の順に並べます。
- 田中英海: 算数を探究的に学ぶ 日常生活を生かした算数授業づくり, 東洋館出版社 (2025).
(p.104)
日常生活でよく使われる道具や設備には、人々の生活を便利にするための構造や仕組みが施されています。例えば、身の回りにある物の形には、平行や垂直の位置関係や対称性が見られます。物を並べやすくしたり、安定感をもたせたりするなど、機能的な意味があります。それらの構造や関係を図形の視点で捉える過程を算数で学ぶことができます。
(写真:省略)
また、身の回りの数量に着目すると、物と物の距離が均等になっていることが多くあります。実践事例の、横断歩道の信号の待ち時間表示のように、二つの数量が比例関係にある場合もよくあります。小学校の算数では、比例関係を前提にして、かけ算やわり算を立式し計算します。物の背景にある構造や関係を数量や式で表すことは、物の構造や関係を解釈できるだけでなく、かけ算やわり算の意味についてもより深く理解することにもつながります。
- 全国算数授業研究会(編著): 算数の学びを愉しむ子ども―没頭する愉しさが探究的な学びへ導く, 算数授業研究シリーズ31, 東洋館出版社 (2025).
(p.104*1)
「いつでもできるよ」という言葉が、子どもから飛び出すのは、どんな時だろうか。「いつでもできる」は、これまでやった問題が「全部できた」とは違う。まだ見ていない問題も含めて、「どれだけ形や数値が変わっても、同じようにできる」という意味を含んでいる。子どもが複数の問題に出合い、その共通の構造を理解し、「なるほど!」と納得した上で、初めて口にできる言葉であると言えるだろう。この「いつでもできる」(一般化)は、大発見なのだ。
- 田中英海: 違いを編む「知性」を育てる指導法, 算数授業研究, 東洋館出版社, No.159, pp.6-7 (2025).
(p.7)
心の働きを引き出し「知性の要素」を体験・獲得させるための発問*2
焦点化する知性の要素 従来の発問 心の働きを引き出す対比的発問 心の働きを引き出す対比的な状況提示 (略) 構造【仕組みを明らかにしようとする】 「きまりがありますか?」 (比較の文脈で)「この2つは全然違うね」 ・複雑やバラバラに見せて,整理したくなる気持ちを引き出す (以下略)
- 田中英海: 1年「ならびかた」, 算数授業研究, 東洋館出版社, No.159, pp.8-11 (2025).
(p.8)
本稿では,「置換・構造」という「知性の要素」の獲得をねらった1年生の実践を紹介する。紹介する単元は「図に表して考えよう」の中で,集合数と順序数のユニット(学習のまとまり)である。集合数と順序数の違いを捉えて,場面の様子や数量を図や式で表すことができることを目指した。また,原問題の条件を変えて問題提示することを通して,子どもが表現や問題の違いを捉えて事象の構造を見出したり,問題の条件を見直したりして,自ら算数の世界を広げようとすることを目指した。
(p.9)
このように元の問題の条件を変えるように提示し,共通の構造を見いだすことで,順序数や集合数について,子どもたち自身で読み替える姿が生まれた。前時に獲得した「置換」という「知性の要素」を発揮しながら,順序数と集合数の違いや,集合数をまとまりとして加法の式で表すという構造を考えることができた。
(p.10)
「5人に減った」と人数の確認があった後,「となりにいるのは同じ数だよ」と比較し,構造に着目する発言が生まれた.(以下略)
なお個人的には,最後に引用した1年「ならびかた」の授業内容は,「構造」と結び付けるのに失敗している事例と,読んで判断しています。とくに気になったのは,「一方,事前の構想でねらっていた4+4-1という重なりを引く反応が生まれなかった。」(p.9)の文です。第1学年の「ならびかた」において,「集合数と順序数*3」「加法と減法」が関連する点に留意し,『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説算数編』p.86などの内容も見比べた上で,「4+4-1という重なりを引く反応」を引き出すことが,「ならびかたの構造」を理解するのに,寄与しづらいように感じられるのです。「事前の構想」としては,ユニットの問題(p.8)がいずれも,並んだ人数を求めるというので共通していた点について,検討の余地があったように見えます。
これまで,「かけ算の構造」について書かれたものを読み,当ブログで見解の整理を試みてきました。そのうち2件にリンクします。
*2:表見出しおよび表の2列目以降は,執筆者(田中英海)のオリジナルと思われますが,算数授業研究 No.159ではp.5やp.12でも,「一般」から「置換」までの順で知性の要素の二字熟語およびその説明を列挙しています。少し検索したところ,https://www.elementary-s.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/r6_kenkyuuhappyou_kiyou.pdf#page=69の図3がおおむね同じです。ただし「分解」の項目を「合成・分解」に変更しているものもあります。
*3:https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/sansu/WebHelp/01/page1_04.html; https://www.mext.go.jp/content/20211102-mxt_kyoiku02-100002607_04.pdf#page=40